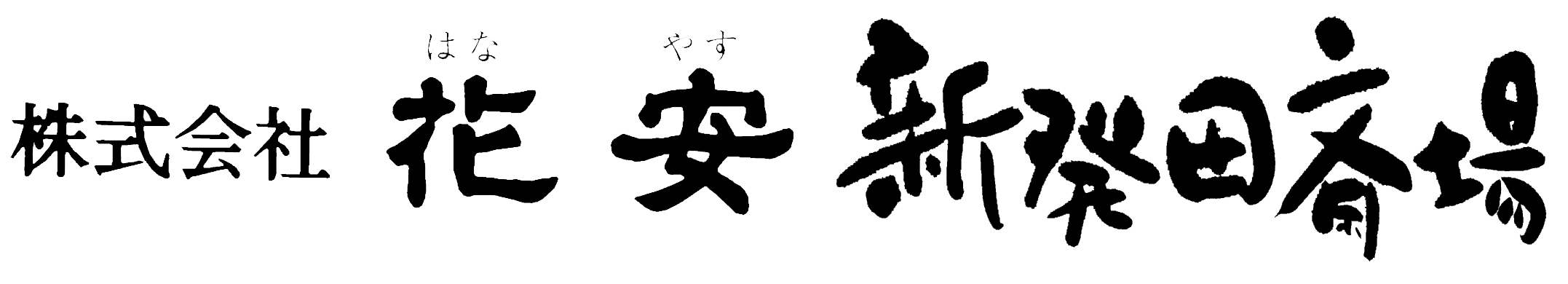株式会社花安新発田斎場様
- 事業内容
- 葬儀施行/法要施行/仏壇仏具/生花/盛り籠/ギフト/生命保険 墓石(提携先にて)
- 従業員数
- 55名
- 設立
- 1989年
- 所在地
- 新潟県
- 課題
- 自主的な社員とそうでない社員が同じ評価基準であることが懸念となり、査定時期の経営陣の負担が大きく評価が見える化されていなかった
人事評価制度を導入後、どのような効果を感じていますか?

年功序列から脱却し、昇給、賞与決定時における経営陣の工数・苦労が大幅に削減されました。
弊社は葬祭業を営んでおりますが、少し前までは業界的に上昇成長しておりましたので、年功序列型の給与でも問題なかったと思います。しかし、業界の動向も変わり、サービス内容が変化してきました。
また、外的要因により企業成長の状況が変わってきている時代に、報酬に見合った業務ができているか疑問な社員、自主的に行動できている社員を同じ基準で評価することに懸念が生じました。
また、導入前は人事評価制度がないので、査定の時期に経営陣は多くの時間を使い、意思決定をしてきました。評価が見える化されていなかったので、給与に関して不公平感を抱く社員もいたと思います。
どんな人事評価制度であれば、弊社に合うのか模索しているときに、あしたのチームに出会いました。
あしたのチームの人事評価制度は、会社の経営理念に基づいた数値目標、行動目標を設定し、かつ自己評価し、頑張った社員は評価が上がり、そうでない社員は評価が下がる、という点を高く評価しています。
マイナス査定を導入するのは覚悟がいることですが、評価基準が見える化され、頑張った社員には報酬で報いることができ、納得感があります。
評価結果が点数化されたので昇給・賞与決定時に頭を抱える時間が一切なくなり、大幅な工数削減となり、経営陣の負担が減りました。
今までは新しいことを実行しようとしてもなかなか思うように勧めることができないという課題もありました。
今は、企業成長するために社員に期待している行動や成果を評価項目に入れているため、社員が会社の方向性にあった行動を取ってくれ、私としては効果を感じていますね。
また今まで中々浸透しなかった面談を定期的に実施することで、コミュニケーションが増えました。導入前はMTGや意思決定の場において、社長や私が介入していましたが、今は私たちが介入しない自主的なコミュニケーション、MTGが増えました。
正直、最初は社員に権限移譲して任せることに戸惑いがありました。しかし、それは私たちの保身で、すべてを知る必要なく、社員に輝いてもらえる環境を整えることが経営陣の職務でもあることに気づかされましたね。
人事評価制度を運用していく中で苦労したこと、また、その局面をどのように乗り越えたのかを教えてください。

昨年度は新型コロナウイルスの影響を受け、業績が下がり、基本給の連動を止めていました。
しかし会社・社員の今後を考え人事評価制度運用は続けていきたい、という希望があり、社員のモチベーションを下げないためにどうしたらいいのか模索し、評価結果のよかった社員に金一封を添えて表彰するという体制を取りました。
給与連動しない状況でも、社員のモチベーションを維持できた背景として、経営数字の見える化を進めていたことが大きな要因かと思います。
いい意味で数字の危機感を感じた中間管理職が、部下達に自分たちは何ができるのか、どう動けばいいのか、声掛けをしてくれていたことだと思いますね。
今の仕事領域だけでは成長は見込めない、今できるプラスのアイディアはないか、この状況でもできる新しい事業は何か?と攻めの姿勢を続けた結果、苦しい状況ではありましたが、社員は本当によく頑張ってくれ、増益で終えることができ、今は給与連動に戻すことができました。
最終承認者が納得できる目標設定ができるようになるには時間がかかりました。
初めて目標設定してみて、苦手としている社員の共通事項は、ITが苦手な人・目標を文章化できない人であることが浮き彫りになりました。
ITが苦手な社員に関しては慣れるしかないですよね。
ただ、弊社は積極的にDX化を進めてきたこともあって、新しいツールの導入には慣れていました。
最初に操作説明し、理解した社員が苦手な社員に使い方をレクチャーする体制が整っていたので、運用がスムーズにいっているのかなと思いますね。
目標を文章化できない社員は、一次評価者のスキルアップで解決できました。
導入当初は、一次評価者が、承認レベルの判断がつかず、2次・3次評価者からの差し戻しが複数回発生し、最終承認まで時間がかかっていました。
しかし、メモ欄になぜ差し戻したのかコメントを残すようにしていたんです。
運用サイクルを重ねることで、メモ欄のコメントを参考にし、被評価者は目標設定のコツをつかみ、文章レベルもおのずと上がりました。
合わせて、一次評価者はこの目標は評価できるか、という視点が養われ、評価者としてレベルアップしています。
今でも多少の課題がありますが、数値目標と行動目標の連動性が取れた、具体的な目標設定ができる社員が増えました。
今後、人事評価制度の運用により、さらに改善したいことを教えてください。

経営陣が人事評価制度に関わらずに、管理職にすべて任せたい、さらに言うと数字の管理まで移譲できたらいいなと思っています。
今の経営陣がその領域の仕事を続けると、中間管理職がその領域にいけないということを意味します。
権限移譲ができれば、その分私たちは違う領域の仕事・事業をすることが可能になります。
もう少し時間はかかりそうですが、実現できることを期待しています。
中間管理職に人事評価制度を任せるにあたり、社員の目線を持ちながら、どれだけ経営者マインドを持てるのかがポイントだと思っています。
大局観を磨き、世の流れを読み、今の立場を理解して、どう現場と経営をつないでいくのか、という視点を養ってほしいですね。
上司は部下のファシリテーターでなければいけません。
答えを与えずに、部下の思いを引き上げ、目指す目標に向かって経営者マインドをもって、実行できる人材になってもらうべく、弊社では教育をしています。
今後、人事評価制度を導入する企業に対してのアドバイスをお願いいたします。

花安新発田斎場の皆様
経営者が楽をしたいと思うのであれば、絶対入れたほうがいいと思います!
業績を上げるために、経営者の力だけではゴールが見えなくなったら、あしたのチームに相談してみるといいと思います。
時代の流れは想像以上に早く、経営者だけの力でどうにかできる時代ではなくなっています。あしたのチームは人事評価制度の構築だけではなく、運用担当者がついて、サポートしてくれています。
担当者がいなければここまで来れていませんでした。他社事例の共有や、次にどんなことが起こるか想定し、先を読んだアドバイスをしてくれたことが、とてもありがたかったですね。
今後はあしたのチームのサポートを卒業し、自社で運用します。運用に関して不安はありますが、あしたのチームが実施しているオンラインサロンを活用し、運用やクラウド操作の知識を深めていきたいと思っています。
クラウドの導入に心配を抱く企業もいると思いますが、
人事評価制度を運用していれば、経営陣が面談に介入しなくとも定期的に面談し、進捗や結果をクラウドに残してくれます。
今までは面談に参加したり、MTG結果の共有を受けないと情報をキャッチアップできませんでしたが、今はクラウドを見れば、MTGの内容や進捗結果は場所を選ばずにみることができるので、大幅な工数削減になっています。