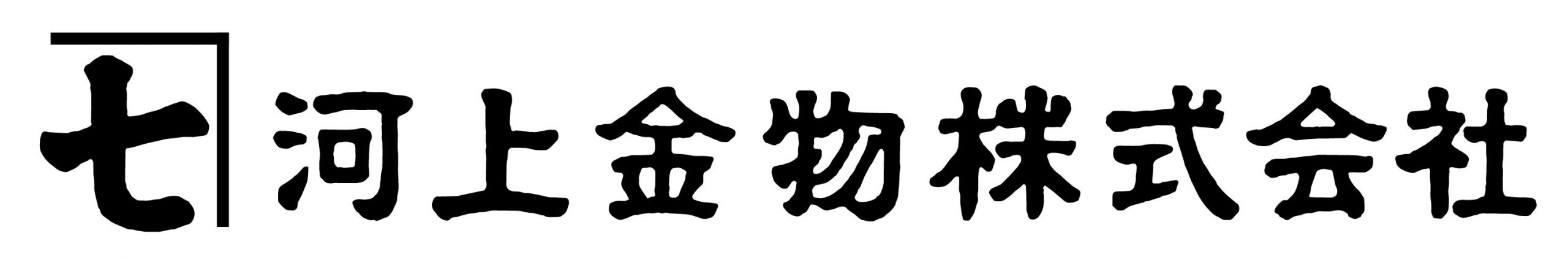河上金物株式会社様
- 事業内容
- 鋼材、各種金物製造・販売
- 従業員数
- 123名
- 設立
- 1946年
- 所在地
- 富山県
- 課題
- 公平な評価を実現し可視化できるようにすることで、社員のやる気向上を目指したい。 社員同士の会話が少なく会社内の報連相が希薄なため、チーム精神を大事にできる環境づくりを実現したい。
人事評価制度を導入後、どのような効果を感じていますか?

社員と管理職が定期的に面談することで、 社内のコミュニケーションが活発になり、 会社としての一体感が生まれたように感じています。
人事評価制度を導入する前は、上司と部下がひざを突き合わせて会話する時間もなかなか取れていませんでしたから、縦のつながりが薄かったんですよね。
中には面談が不得意な管理職もいますが、管理職という立場上、やらないという選択肢はないと思います。私が面談同席する被評価者は課長職以上ですが、運用サイクルを重ねるごとに、目標設定に対するアドバイスなど、面談の質が上がってきていることも実感しています。
今後は、目標・評価の面談をすることで仕事の悩みや今後の展望まで、腹を割って話せる。そんな関係性が築いていけるといいなと思っています。
また、人事評価制度を使って、企業理念が浸透できるようになりました。
弊社は、事業承継を迎えていた時期に導入しましたが、以前社長が実施していたことを、私がそのまま継承するにしても、時代に合わせてやり方を変える必要があると思っていたんです。
以前は、社長と社員は以心伝心で社長が求めることが社員に自然と通じていたので、企業理念を改めて伝えなくても、会社が求める行動ができていました。
しかし、新入社員も増えてきて、時代のせいもあるのでしょうか。以前ような以心伝心では何も通じなくなってきたんです。
人事評価制度は、行動目標の項目欄に、目標を選定した理由とどんな目標を立てて欲しいのかを記載しますよね。それによって、会社が社員に求めている行動が可視化されて伝わるようになり、理念の浸透に大きく繋がったと実感しています。
人事評価制度は、社長が大切にしていたものを言語化し、それに向き合うことができるツールだと思いました。事業継承の大事な時期に、人事評価制度を導入していて良かったです。
別の面で言うと、あしたのクラウド®で管理工数を削減できました。
弊社は元々紙で人事評価を実施していましたので、印刷して書いて集計して…それだけでも手間がかかり、今とは比べ物にならないくらい管理工数がかかっていたんです。
現在は、あしたのクラウド®で直近の目標から過去の評価結果まで容易に確認管理ができて非常に助かっています。
中には紙の方が良いという社員もいますが、あしたのクラウド®は評価シートをExcel資料でダウンロードできるので、印刷して渡すことも簡単です。
私自身は紙よりもデータで情報を管理したかったので、あしたのクラウド®は使いやすくて気に入っています。
あしたのクラウド®で部下の頑張りや目標をいつでもどこでも見られるところも、あしたのチーム®に決めて良かったと思えたことの一つです。
人事評価制度を運用していく中で苦労していることを教えてください。

最初に苦労したのは、管理職からの反発でした。弊社は初期導入の際、管理職のみでトライアル運用を始めたんです。
あしたのチーム®を導入する前は評価制度がなかったので、まずは、社員に制度を理解してもらうことから始める必要がありました。
まずは、一次評価者が人事評価制度を理解することが最重要だと考えて管理職のみを対象に運用を開始しましたが、行動目標が9項目あることが原因で反発が起きました。
項目数が多く「日々忙しいのにこんなにたくさんの目標はできない。」といった目標と日々の仕事を切り離して考えてしまうような事があったんです。これは、想定外でしたね。
しかし、社員に運用に慣れてもらうことが優先だと考え、一般社員を含めた全社員での運用を始める時に、項目数を4項目まで減らすことにしました。
他にも、管理職だけで運用をしていた時は、制度に対する理解度や目標の難易度に人によってバラつきがあったので、頭を悩ませていましたが、余計な心配でした。(笑)これは、一般社員まで対象を広げたことで改善されたんです。
被評価者側の立場だった管理職が、評価者側に回ったことで、自然と人事評価制度の理解が深まり、目標設定や評点のつけ方のコツをつかんだからだと思います。
また、社員目線で言えば、四半期の評価期間の運用が、正直ハードルが高く、大変だったと思います。四半期の運用ですと、ほぼ毎月評価イベントが発生するため、運用当初は社員も、「また期日の催促連絡か」と思っていたと思います。しかし、1年間で4回の運用を繰り返したことで、自然とそのペースに慣れてきています。
今では、四半期サイクルを「大変だ」と感じるのではなく、“そういうもの”という認識で運用できるようになりました。何事も、継続することって大事ですね。
また、弊社が1年で社内に運用を定着することが出来た理由は、期日管理を徹底しているからだと思います。四半期は短いので、少し目標設定の期日がずれてしまうだけで、目標を達成するための期間が短くなり、結果的に達成のための行動に移せないまま評価期間が終わってしまう…。それでは、社員が成長できず、人事評価制度をやっている意味がありません。
期日を守ることは、人事評価制度を使って社員の成長を促すために特に大事なことなので、弊社は常務である私が期日のリマインドをしているんです。経営陣が直接働きかけをすることで、会社の人事評価制度に対する真剣さが伝わったのだと思います。
最後に、今も苦労しているのは、目標設定や評価のためだけの制度になっていることです。どうしても、人事評価制度をやっつけ作業や他人事として捉えてしまっている人がいるんですよね。
人事評価制度は、“自己成長のためのツールであること”と認識して、自主的に取り組んでもらいたいです。これを解決するには、もう少し時間や経験が必要かなとも思っていますが、「立てた目標を達成することで報酬が上がる」というリアリティーを感じてもらうことが必要だと思い、運用2年目となる先月から評価結果を報酬に連動させています。
まずは人事評価制度に慣れてもらいたくて、導入してから1年間は、評価結果を報酬に連動させず、トライアル期間として運用をしていたんです。
報酬連動することによって、自分の頑張りが評価に反映し、その結果が昇給や昇格に繋がることが実感できると思うんですよね。
この実感を繰り返して積み重ねていくことで、おのずと人事評価制度を自分事としてとらえることができるのではないでしょうか。これから初めての査定を経て、頑張りが昇給・昇格に繋がることを実感できた社員が、どのような変化を見せてくれるのか、楽しみにしています。
今後、人事評価制度の運用により、実現したいことを教えてください。

人事評価制度を活用して、私の理想とする職場環境を実現したいです。
私は、上司と部下間であっても、仕事に対する疑問や改善案を気軽に意見交換できるような関係を理想としています。
人事評価制度というツールを通じて、上司が部下の目標を管理することで、面談以外の場所でも目標達成に対するアドバイスや、仕事の課題に対する相談ができる関係性が醸成されて、目標を達成することで成長し、その成長を部署みんなで称えられる、そんな事象が各部署で起こることを望んでいます。
近年は、若い社員も増えたことで、部署の壁がなくなり、横の連携も増えてきていますが、壁を作り自分だけで完結してしまう社員がいるのも事実です。
今後は人事評価制度を通して、全社の目標を達成するための部署を超えたプロジェクトができて、連携が増えるなど、全社員が壁をなくして協力しあえる社内風土ができればいいなと思います。
また、会社の中には様々な役割があり、一人ひとりが与えられた役割に全力で邁進することで、企業が成長します。“船は進んで当たり前、乗っていれば目的地につく”というような他人任せの考えの社員がいては、企業は成長しません。
会社の成長のためにも、人事評価制度で自分の役割を理解し、達成に向けて取り組むことで、全社の目標も自分事として捉えられるようになり、会社や社員の共同体意識がより醸成されることを期待しています。
今後、人事評価制度を導入する企業に対してのアドバイスをお願いいたします。
人事評価制度の導入で一番大事なのは、経営者のコミットメントだと思っています。
会社の環境は、100社100通りありますし、あしたのチームさんに任せているだけでは、本当に自社に合った人事評価制度を作ることはできません。
あしたのチームさんから提供された情報は、そのまま会社に適用するのではなく、自社に合うか合わないかを判断する必要があります。
あしたのチームさんは、豊富な知識や人事評価制度を構築、運用するための材料提供をしてくれますが、それを、「この部分は自社にも合っているからこのまま取り入れてみよう」「この部分は、自社だと少し違っているから、こんな風に変えてみよう」と、自社に合ったものになるように工夫して運用するのは、私たち経営者の判断です。
誰よりも私たち経営者が責任もって運用していくことが大事だと思います。
また、あしたのチームさんと会社の間に入って橋渡し役となる“運用担当者”を誰にするか、 これも肝心です。
人事評価制度は、正直聞きなれないワードも多く、あしたのチームさんからもらった情報をそのまま社内に流すだけでは、本当の意味で浸透させることができないと思います。
「うちの社員には、こうやって伝えると伝わるかな?」など、自社に合った言葉に変換しながら、社内に浸透させていける人に任せるようにしてください。
私は、特に弊社のような規模の会社であれば、人事担当者に完全に運用を任せるのではなく、まずは会社のリーダーである経営者が旗振り役となって、制度の運用に積極的に参加していくことをお勧めします。