
モチベーションとは、社員が仕事に熱意を持って取り組む源泉になります。
モチベーションが高い社員は、自主的に業務に取り組み高い成果を発揮します。しかしながら、高いモチベーションの維持には、整った就業環境や高い給与だけでは十分とはいえません。
ここでは、モチベーションの意味や向上の理論を解説し、社員のモチベーションアップにつながる方法について紹介します。
目次
モチベーションとは
モチベーションとは、「やる気」「意欲」「動機」という意味で用いられる言葉です。組織においては、社員が企業やチームのミッション達成に積極的に貢献しようという動機付けのことを指します。
人事領域では、社員が仕事へ取り組む自主性などを育む要因として重視されます。働くモチベーションには、労働条件や職番環境のほか、人間関係や業務内容などさまざまな要素が関係します。
また、個人によって重視するモチベーションの動機づけは異なります。自社の社員それぞれにとって、仕事の意欲を掻き立てる要因がなにであるか、適したアプローチ方法を検討することが重要です。
モチベーションの使い方・例
モチベーションという言葉は、ビジネスシーンでもよく使われます。シーンに合わせた使い方ができるように、例文を確認しておきましょう。
モチベーションが上がる
モチベーションが上がるとは、やる気や意欲などが高まることです。
【例文】
- 彼は昇進が決まってモチベーションが上がっている
- 部下のモチベーションを上げるには、ほめることが大事だ
言い換え例としては、「モチベーションが高まる」「モチベーションが向上する」などがあります。
モチベーションが下がる
モチベーションが下がるとは、やる気や意欲などが低くなることです。
【例文】
- 業績悪化によって、従業員全体のモチベーションが下がっている
- 人事評価の不公平感はモチベーションを下げる要因だ
言い換え例としては、「モチベーションが低くなる、低下する」「モチベーションが落ちる」があります。
2種類のモチベーション
動機付けが内からくるのか外からくるのかによって、モチベーションは「内発的モチベーション」と「外発的モチベーション」の2つに分けられます。それぞれについて解説します。
内発的モチベーション
内発的モチベーションとは、本人の内面から動機付けられたモチベーションです。たとえば「憧れの職種に就けた」「顧客の役に立っている」など、自己実現とリンクしているのが特徴です。
したがって、内発的モチベーションを持った従業員は、目標そのものに対して自発的な意欲を持ちます。外部からの働きかけがなくても、モチベーションが長く続く傾向があります。
一方、内発的モチベーションは組織の要求と根本的に無関係です。内発的モチベーションを実現するために離職するようなケースもありえます。
外発的モチベーション
外発的モチベーションとは、外から動機付けられたモチベーションです。たとえば、給与アップや昇進などによって外発的モチベーションは高まります。
外発的モチベーションは、組織マネジメントや人材育成によって向上させやすいのが特徴です。その反面、人事担当や上司など、モチベーションを与える側の負担は増します。また、インセンティブを与えたり、職場環境を整えたりすることでコストが発生する場合もあります。
社員のモチベーションが低下する理由
ほとんどの社員は仕事にやりがいを持ちたいと思っているはずです。それではなぜ、モチベーションが低下してしまうのでしょうか。ここでは企業側で対応できる原因を中心に解説します。
仕事にやりがいがない
本人の意向と実際の業務にミスマッチが生じることで、モチベーションが下がる場合があります。たとえば、接客が好きなのに、在庫管理に割り当てられたようなケースです。このような場合、ミスが出やすく、能率も人より劣ってしまい、ますますモチベーションが下がってしまうでしょう。
適切な人材配置ができない原因としては、本人のキャリアプランを十分聞き取れていないケースや、スキル・適性を見抜けていないケースなどがあります。
報酬や人事評価に不満がある
自分の働きに見合った対価を受け取れない場合も、モチベーションが下がります。たとえば、年功序列制度を採用している企業は、勤務年数で給与や昇進などが決まります。このため、「何をしても変わらないから、手を抜こう」などと、無気力になる社員が増えてしまいがちです。
また、人事評価に公平性、客観性がない場合も、モチベーションが下がってしまうでしょう。特に成果物がなく評価基準があいまいになりやすい業種では、「頑張っているのに評価されない」と思われ、モチベーションが下がる傾向にあります。
業務量が多すぎる
能力を超えた業務量を与えられ続けられると、モチベーションを失ってしまいます。創意工夫を図る余裕がないことや、プライベートでリフレッシュする時間を持てないことなどが原因です。
特に本来の業務以外の負担が重いと、モチベーションが低下します。たとえば「電話応対で時間を取られてしまう」「アナログ作業が多く非効率」といった原因で残業が増えれば、本業への意欲を削いでしまうでしょう。
会社の社風や方向性に納得できない
社風や経営方針になじめない社員も、モチベーションが低下しがちです。「体育会系で上下関係が厳しい」「利益優先主義で顧客のことは後回し」などのケースです。
多くの社員は自分らしく働きたい、仕事を通じて自己実現したいと考えています。社風や方向性のミスマッチは、こうした内発的モチベーションの実現をさまたげてしまいます。このモチベーション低下が多くの社員にみられる場合は、組織が時代に合わなくなっていると疑ったほうがよいでしょう。
モチベーションの低下が企業にもたらすリスクとは
社員のモチベーション低下は、組織の問題に発展します。モチベーションが下がり自主性や責任感が希薄になった社員は、組織の生産性も下げるからです。時には、企業の存続にかかわる大きな事故や不祥事の原因になってしまいかねません。
ここでは、上記のようなモチベーション低下が企業にもたらすリスクについて解説します。
社員の自主性が損なわれる
モチベーションが低下すると、まず仕事に対する創意工夫が起きず作業効率が低下します。与えられた仕事をそのまま行うというように、業務に取り組む過程で改善などが行われなくなります。
結果として、ノウハウやナレッジが蓄積されなくなり、組織としての競争力を失ってしまうでしょう。また、創造性豊かなアウトプットが出にくくなり、イノベーションを起こせない企業になってしまいます。
責任感やコンプライアンス意識の低下
モチベーションが低下すると、事業に対する貢献意欲が低くなります。ひいては仕事への責任感やコンプライアンスも欠如しがちです。
その結果、ミスやインシデントが発生しやすくなります。また、個人の無断欠勤や遅刻といった規律を無視した行動も多くなります。場合によっては、重大な事故や不祥事につながってしまうでしょう。
生産性が下がる
従業員のモチベーションとパフォーマンスは相関関係があることが知られています。モチベーションが低い社員が増えれば、組織としての生産性も下がってしまいます。
モチベーションの低い社員がボトルネックになるケースが多いことにも注意が必要です。たとえば、モチベーションが低い上司がいれば、部下たちも悪い影響を受けてしまいがちです。
また、モチベーションが低い社員をカバーするために、チーム全体が足を引っ張られるケースもあるでしょう。モチベーション低下は一個人の問題ではなく、組織に波及する問題として捉えるべきです。
退職者が増加する
モチベーションが低下した社員は、最終的に離職してしまいます。少子高齢化により労働力不足が進む日本において、人手不足は致命的なリスクになりかねません。
よくあるケースは、業務負荷が大きい中堅社員が、モチベーションの低下で辞めてしまうケースです。中間層がいなくなれば、管理職が若手社員に無理な要求をする、ブラックな職場が誕生してしまいます。そうなれば、ますます人材確保は難しくなり、経営が困難になるでしょう。
モチベーションを上げることの効果
では個人のモチベーションが向上することで、どのようなメリットが企業にもたらされるでしょうか。
1.生産性のアップ
ひとつは、生産性のアップです。仕事への意欲が高まることで、創意工夫を凝らすようになります。業務フローが複雑であれば、機械化や省力化の道を試すようになるでしょう。新たなアイディアを実践しようとプロジェクトを立ち上げるかもしれません。
このように、社員自らの働きかけによって仕事の成果が変化し、評価されることでさらにモチベーションを高めていくという、正のサイクルが生まれます。
2.企業競争力の向上
社員のモチベーションが高い企業は、生産性がアップし、自社サービスや商品が持続的に改善・改良されていきます。顧客の声に耳をかたむけ、サービス向上への努力を惜しみません。市場から求められているアウトプットを模索し、よりよいサービス作りに努めます。
このような仕事への取り組みは長期的には企業の業績に反映されます。また、仕事への熱意が高い社員がいることで、同じように働くことにやりがいを感じ、挑戦心を持った社員が集まってきます。
3.離職率の低下
モチベーションが高い社員は、働くことで充実感を得られます。日々の業務で創造性を発揮し、仕事を通じて自らの変化を実感します。いまの職場が正しい選択であり、中長期的なキャリアアップにつながると実感できます。
そうした社員にとっては、仕事は単純に稼ぎを得るためのものだけではありません。労働条件や職場にネガティブな印象を抱いても、仕事の充実感というポジティブな印象があるため、結果としてその職場で働き続けることを選ぶでしょう。
モチベーションを計測する方法
従業員のモチベーションを調査・計測する方法として、モチベーションサーベイがあります。モチベーションサーベイの定義や方法、メリットについて解説します。
モチベーションサーベイとは?
モチベーションサーベイとは、仕事に対する社員のモチベーションの度合いや内容の調査です。収集したデータの分析や評価も含まれます。
モチベーションサーベイは主にアンケート形式で実施され、質問項目は後述するモチベーション理論に従って選びます。たとえば、「あなたは仕事に誇りを持っていますか」「過去1週間で、成果に対する評価を得られましたか」などです。
ただ、モチベーションサーベイの範囲は広いため、自社の課題に合わせてカスタマイズしなければならないケースもあります。知見がない場合には、コンサル会社やHR企業に依頼するのがよいでしょう。
モチベーションサーベイの実施方法
モチベーションサーベイは、従業員満足度調査や従業員ロイヤルティ調査をかねて、年1回程度実施するのが一般的です。企業に対する従業員の愛着や信頼感、貢献意欲は、モチベーションと深い関係にあるからです。
モチベーションサーベイは、どのような目的で実施するか周知させてからアンケートを行い、データを集計・分析する流れとなります。アンケートを記入してもらう際は、必要に応じて匿名性、プライバシーに配慮しましょう。
モチベーションを計測するメリット
モチベーションサーベイのメリットは3つあります。
1つ目は従業員のモチベーションの現状を数値化して把握できることです。定期的に実施すれば、時系列で推移を確認できるでしょう。
2つ目はモチベーション低下・向上の要因を特定できる点です。問題があれば改善し、成果が出た施策があれば横展開するなど検討します。
3つ目は今後の経営戦略や人事施策などのヒントにできることです。仮に仕事が先細りでモチベーションが低下している社員が多ければ、リスキリング(学び直し)を検討するなど、組織運営のヒントを得られます。
モチベーションマネジメントとは
会社でモチベーションを上げるためにできることとして、モチベーションマネジメントがあります。モチベーションマネジメントとは、従業員が高い意欲を持って仕事に取り組めるように動機付けを行い、サポートするマネジメントです。
モチベーションマネジメントは、人材育成や人材定着のプログラムとして実施されるのが一般的です。たとえば、内発的モチベーション向上なら、キャリアアップのための資格取得を支援する施策が挙げられます。外発的モチベーション向上なら、公平な人事評価制度の整備や福利厚生の充実などがあります。
この記事ではモチベーションを高める方法を解説していますが、これらはモチベーションマネジメントの一種だと考えてください。
モチベーションを解明する2つのアプローチ方法
では、このように人や組織に影響を与えるモチベーションとは、いったいどのような要因でどのように人々に作用するのでしょうか。
見えない人のモチベーションを理解するのに役立つのが、これまでに行われてきたモチベーションについての研究と理論です。モチベーションの研究は諸説ありますが、大きく分けて「組織メンバーが持つ欲求に重点を置く」理論と、「メンバーがモチベーションを高めていくプロセスに重点を置く」理論の2つがあります。
1.組織メンバーが持つ欲求に重点を置く理論
この理論は、モチベーションの内容に関するアプローチ方法です。人が何かに取り組むとき意欲を起こさせるものの「中身」について研究しています。モチベーションの欲求説、もしくは内容説ともよばれます。
人は共通したモチベーションへの欲求を持っているという考えがベースになっており、代表的な例としては欲求の内容をピラミッドのように配置した「マズローの欲求階層説」や、外側から与えられる動機と内面から湧きあがる動機とに分類した「ハーズバーグの動機付け衛生理論」があります。
2.メンバーがモチベーションを高めていくプロセスに重点を置く理論
こちらの理論では、モチベーションの発生する内容(欲求)ではなく、モチベーションが動機付けられるプロセス(過程)に重きを置いています。過程説、文脈説ともよばれる考え方です。
この理論のベースには、人々のモチベーションがあがる内容は、状況や条件によって異なるという考えがあります。
代表例として、最初にモチベーションの仕組みを明示した「ブルームの期待理論」があります。
知っておきたい6つのモチベーション理論
モチベーションについてさらに理解を深めるために、上述した2つの研究アプローチ方法について、属する代表的な理論を6つ紹介します。
欲求説①マズローの欲求段階説
人は自己実現のために絶えず成長する生き物だという考えを根幹としています。人の欲求には、「生理的欲求」「安全欲求」「社会的欲求」「承認欲求」「自己実現欲求」の5つがあり、生理的欲求を一次欲求として、下位の欲求が満たされると上位の欲求が生じるというものです。
生理的欲求は食欲や睡眠欲、安全欲求は外敵から身を守りたいという欲求を指します。これを現代におきかえると、生理的欲求は衣食住を満たす雇用を得ることであり、安全欲求は雇用を失うことがない保障であるといえます。
これらの低次の欲求がみたされると、人は同僚や仲間との一体感や仕事を通じて社会に貢献しているという社会的欲求を満たしたいと思うようになります。そしてより良い評価を求め承認欲求を満たすようになり、自己実現欲求として自らの能力を最大限発揮できる自分を目指すようになります。
欲求説②マグレガーのX理論、Y理論
マズローの欲求段階説を、経営的観点からさらに深めたのがマグレガーのX理論、Y理論です。この理論では、人の本性を「仕事嫌いで怠け者なネガティブな面(X部分)」「自己実現したいポジティブな面(Y部分)」にわけ、それぞれに対する管理者の行動様式をX理論・Y理論として説明しています。
X理論では、人はなまけたがる生き物のため、アメとムチと呼ばれるような厳しい管理体制にする必要があります。命令や強制で人を動かし、達成度合いによって賞罰を与えます。
対してY理論では人は進んで働きたがる生き物です。そのため、管理者がコントロールするのではなく社員に裁量を多く持たせ、協力関係を築くことが重要になります。
生活水準が向上し、生理的欲求や安全欲求が満たされている現代では、X理論のような厳しい管理体制ではモチベーションを向上させる効果は低く、むしろY理論に基づいたマネジメントが求められると考えられています。
欲求説③ハーズバーグの2要因理論
ハーズバーグの2要因理論では、企業で社員が不満を招いた要因と満足を招いた要因を分けて整理しています。
不満を招いた要因には、労働条件、給与、身分、安全、マネジメントの在り方などがありこれらは「衛生要因」と呼ばれます。一方、満足を招いた要因には、達成感、他者からの評価、仕事への満足感、責任、昇進などがあり、「動機付け要因」と名付けられました。
この理論で注目されるのは、衛生要因である労働環境や給与は不満の要因にはなっても、改善したところで社員の満足度向上にはつながらないという点です。
仕事の不満を生み出す原因を改善してもモチベーションは向上せず、意欲を引き出すには動機付け要因を高めることが効果的です。
とりわけ、給与は社員の働く動機付けと考えられがちですが、衛生要因に位置付けられています。社員のモチベーションを高めるには給与アップを行うだけでなく、人事評価と連動した制度を構築することが重要です。
過程説①ブルームの期待理論
現代モチベーション理論の代表例であるブルームの期待理論は、人の行動は、定められた報酬につながる期待と、達成される成果が本人にとってどれだけ魅力的であるかという考えをベースにしています。
モチベーションを引き起こす誘因に、「対象の魅力度」「達成への直結度」「実現の可能性」の3つをあげ、これらを掛け合わせたものが高いほどモチベーションが高まるとします。
対象への魅力度は、本人によって異なります。いくら一般的に魅力的な報酬が用意されていたとしても、本人が魅力に感じなければモチベーションの高まりは発生しません。達成への直結度は、言い換えればどれくらいの努力で達成できるかという見通しです。
途方もない努力が必要と感じれば、本人のやる気は低下してしまうでしょう。実現の可能性とは、行動し報酬を手に入れられる確率を指します。
期待理論では、まずは社員にとって魅力が高い結果を用意する必要があります。重要なのは、会社が考える魅力ある結果と社員本人が考える魅力ある結果をすり合わせることです。つぎに、結果を得るための目標と達成までのプロセスを明確にします。そしてさらに、本人が達成可能性を感じられるよう、サポートするマネジメントが求められるでしょう。
過程説②衝平理論
衝平理論とは、人が他者と比較し、不公平を感じる場合に公平性を感じるような行動をとるとされる理論です。
組織のなかで、社員は報酬(アウトプット)に対する満足度を、自分が投入した努力や経験(インプット)だけでなく、他者のアウトプットとインプットの比率を用いて考えます。
たとえば、自分が努力で得た報酬の比率が他者のそれよりも小さい場合は、低報酬と認識します。逆に、自分の努力で得た報酬の比率が他社のそれよりも大きい場合は、高報酬と認識します。
不公平を解消するための行動としては、仕事を熱心にしなくなったり、不当な手段で成果を大きくしたりすることが考えられます。不公平を感じている社員へは、給与改定などのアウトプットの変更や、具体性のある評価の提供といった働きかけが必要です。
過程説③目標設定理論
目標設定理論とは、目標への認識とモチベーションの関係を明らかにしたものです。
困難な目標があり、それを本人が自分ごととしてとらえ達成することでモチベーションが向上します。このとき、達成には適切なフィードバックが必要です。
目標設定理論では、目標を達成し、行動と結果が適切に評価を得、報酬を得ることが満足感を生み出しモチベーションを向上させるとしています。このサイクルによって、人は自らの行動で目標を達成できるという自己効力感を強め、さらに困難な目標に立ち向かうことが可能になります。
東京海上日動リスクコンサルティング
モチベーションを上げる5つの方法
紹介した6つの理論で異なる角度からモチベーションが解明されているように、モチベーションを向上させる唯一の正解があるわけではありません。
しかしながら、各理論は企業でのモチベーション向上施策を考える大きなヒントになります。ここでは、モチベーション向上につながる制度や仕組みを4つ紹介します。
1.プロセスが明瞭な目標管理制度
目標管理制度(MBO)とは、個人の目標を設定しそれに対する達成度合いで評価を決める制度のことをいいます。組織とリンクした個人の目標を、社員が自主的に設定することで「やらされる感」が減少します。
本人が魅力に感じる目標や目標への納得度が、目標を達成できるという自信を高めモチベーションの向上につながるのです。
目標管理制度は、社員が自主的に目標設定をするだけではなく、上司と部下がコミュニケーションを取りながら適切なフィードバックを用いて、目標達成までを支援することが大切です。
さらに、成果だけでなく達成までの行動が、明確な評価基準で評価されることで、より納得度の高い管理制度となります。
2.公正公平な評価制度
目標を達成し、報酬を経ても、その評価が不公平だと感じる場合社員のモチベーションは向上しません。たとえば評価者によって基準にばらつきがあると公平であるとはいえません。
さらに、評価基準が不明確な場合、評価された内容へ不満を抱くようになります。
公正公平な評価制度を構築し、かつ運用するには、管理者の主観的な判断だけにゆだねるのではなく、コンピテンシー評価など基準が確立されている制度を導入し、自社の状況にあわせ構築する必要があります。
また、評価制度システムを用いて目標・評価を可視化することも重要です。
3.福利厚生の充実
ここでいう福利厚生とは、キャリアアップにつながるような教育・研修機会の提供や、育児や介護関係のサポートのことを指します。
仕事に関連したスキルアップは、達成感や満足度を高め、内的動機付けにつながります。さらに、ベビーシッター費用の補助など、仕事と両立する必要のあるサポートが充実していることで、安全欲求や社会的欲求が満たされます。
自らの成長に会社が投資してくれていると感じ、社員と組織の信頼関係構築につながります。
4.社内コミュニケーションの促進
コミュニケーションが活性化された職場では、社員のモチベーションが高まりやすいことが知られています。コミュニケーションを増やせば、お互いに評価、協力し合うことでモチベーションを高められます。
また、率直な意見を述べられる職場であれば、上司への失望感や職場への無力感など、モチベーションを下げる要因が少なくなるでしょう。
5.それぞれにとっての最適なモチベーションの状態を考える
モチベーションアップの施策は、すべての社員に対して行うのではなく、それぞれの特性や個人の考えを反映させることが大切です。
人によって、なにが魅力的な目標になるかは異なります。キャリアアップのため、チャレンジングな仕事に挑戦したい社員もいれば、家庭と仕事のバランスを維持したいという社員もいます。
個々の社員のモチベーションの動機となる理由をヒアリングしながら、適した施策を選ぶ必要があります。
モチベーションを管理する際の注意点
社員の心に働きかけるモチベーションマネジメントは、細やかな配慮が必要です。
ここでは施策を問わず共通の注意点として、「プライベートに介入しない」「目標設定は具体的に行う」「会社の都合を押し付けない」の3つを解説します。
プライベートに介入しない
社員のモチベーションを高めたい場合でも、プライベートまで介入するのは止めましょう。たとえば「家庭よりも仕事に集中するべきだ」「お酒の量を減らせば、やる気が出るはず」などとアドバイスすれば、人格否定やハラスメントになりかねません。
モチベーションマネジメントは仕事に関するモチベーションを高めようとする手法です。あくまで業務領域に限って働きかけるとよいでしょう。
目標設定は具体的に行う
モチベーションアップのために目標を決める際は、具体的にしましょう。なるべく達成度を明確に把握できる数値や成果物で設定します。また、短期的目標と長期的目標に分けるのもよい方法です。
具体的な目標があれば、社員は自主的にゴールに向けた方法や努力を考えるようになります。創意工夫のアイディアも出やすくなるでしょう。
また、具体的な目標があれば周囲も評価をしやすくなります。それによってモチベーション維持に必要な社会的欲求や承認欲求も得やすくなるでしょう。
会社の都合を押し付けない
会社から一方的に動機付けをするのは逆効果になるリスクがあります。プラス思考を強要したり、一方的に目標を押し付けてモチベーションを高めようとしたりしても、本人が受け入れるとは限りません。
モチベーションマネジメントは内発的モチベーションと外発的モチベーションが近いと、効果が出やすい傾向があります。したがって、はじめに社員の意向を聞く機会を設けるとよいでしょう。会社から動機付けする場合にも、メリットを伝えて本人の納得を得るプロセスが欠かせません。
企業のモチベーションアップ成功事例
ここでは社員のモチベーションを高められた企業の成功事例を4社紹介します。
リクルートの新規事業提案制度
大きな企業ほど、個人は組織の歯車のようになり、モチベーションを失ってしまいがちです。リクルートは事業に参画意識を持ってもらい、やりがいを持てる仕組みとして「新規事業提案制度(Ring)」を導入しました。
Ringは社員なら誰でも自由に参加できる提案制度です。既存・新規領域を問わず、取り組みたい内容を提案し審査を通過すると、一定の活動費が支給されたうえで新事業をスタートできます。
実は「ゼクシィ」「R25」「スタディサプリ」などは、Ringを起点に花開いた事業です。1990年に始まった制度はリニューアルを続け、リクルートの価値創造の源となっています。
資生堂のカンガルースタッフ制度
女性社員の多い資生堂は、仕事と子育ての両立支援に課題を持っていました。
そこで構築したのが「カンガルースタッフ」というサポート制度です。育児中の社員は子どものお迎えや夕食準備などの家事のために、早めの帰宅が認められています。その際にバックアップするのは、100時間の研修を受け、顧客の買い物をサポートできるレベルまでになった契約スタッフです。
カンガルースタッフ精度によって、育児を理由にした離職が減り、専門知識を持った社員を育成しやすくなりました。
ザ・リッツ・カールトンのファーストクラス・カード
世界中にホテルを持つザ・リッツ・カールトンは、スタッフ同士で感謝の気持ちが回る仕組みを作りたいと考えていました。そこで考案したのが、顧客のほか、同僚、上司、部下に感謝を伝える「ファーストクラス・カード」です。
あえてカードにしたのは、口頭によるお礼でなく、形に残るもので明確に気持ちを伝える習慣を作るためでした。カードをスタッフの食堂に貼ってシェアされる仕組みも取り入れています。
ファーストクラス・カード導入以降、助け合いと尊重し合う精神が養われ、それがサービス向上、顧客満足度向上につながっているということです。この好循環を支えているのが、お礼を言われたスタッフのモチベーション向上にほかなりません。
サイボウズのモチベーション創造メソッド
大手ソフトウェア開発会社のサイボウズは、できること・やりたいこと・やるべきことの3領域を重ね合わせてモチベーションを創造する「モチベーション創造メソッド」を導入しています。
できること・やりたいことを掛け合わせることで、現実的でやりがいのある活動が決めやすくなります。さらに、やるべきことをかけ合わせれば、企業ニーズと個人のモチベーションを一致できる仕組みです。
サイボウズが先進的なのは、グループウェアを用いて創造プロセスを共有している点です。企業はやるべきことを書き込み、個人はできること・やりたいことを書き込むことで、適材適所の人材配置が促され、組織運営と個人のモチベーション向上を融合できています。
社員のモチベーションアップを促し働きやすい会社を目指そう
社員のモチベーション向上には、なにが動機付けになるのか社員の声を聞くことが大切です。そして目標は会社が押し付けるノルマではなく、社員のマネジメントの一貫として位置づけ、明確な評価基準や適切なフィードバックを用いることで、目標達成度合いを高めることができます。
納得度の高い目標を達成し、魅力ある報酬を得ることが、モチベーションアップのサイクルを生み出します。

組織づくりに関連したおすすめセミナーのご案内
あなたにおすすめのお役立ち資料を無料ダウンロード
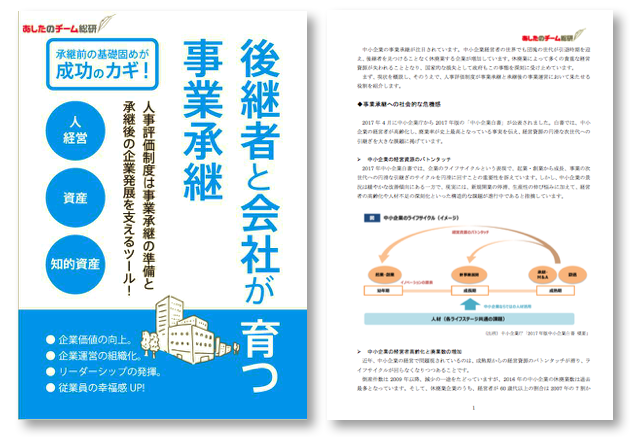
ダウンロードは下記フォームに記入の上、送信をお願いいたします。
【無料eBookプレゼント】後継者と会社が育つ事業承継
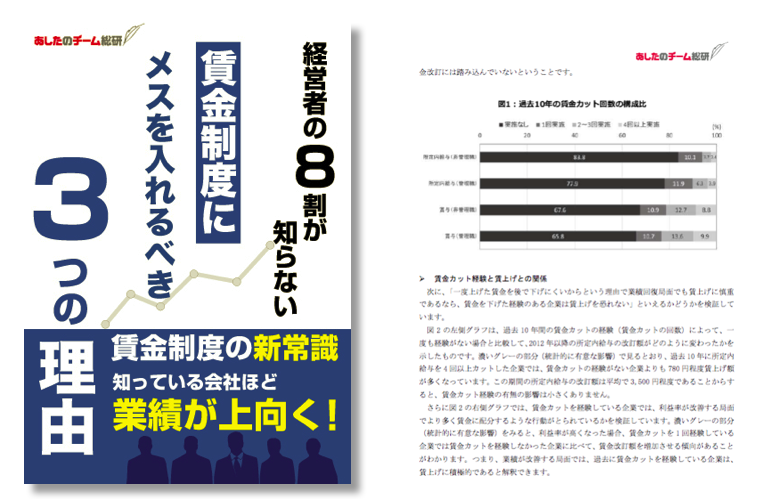
ダウンロードは下記フォームに記入の上、送信をお願いいたします。
【無料eBookプレゼント】8割の経営者が知らない 賃金制度にメスを入れるべき3つの理由
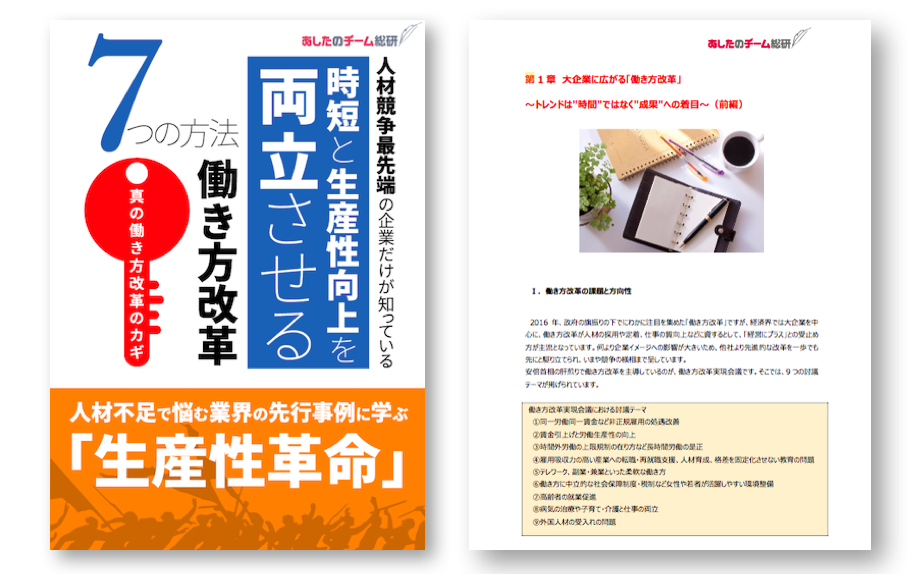
ダウンロードは下記フォームに記入の上、送信をお願いいたします。
【無料eBookプレゼント】時短と生産性向上を両立させる働き方改革7つの方法
組織づくりの課題を解決するサービス紹介
あしたのチームのサービス
導入企業4,000社の実績と12年間の運用ノウハウを活かし、他社には真似のできないあらゆる業種の人事評価制度運用における課題にお応えします。

ダウンロードは下記フォームに記入の上、送信をお願いいたします。
サービスガイド

ダウンロードは下記フォームに記入の上、送信をお願いいたします。
あした式人事評価シート
 あしたの人事オンライン 「あした」を変える「人事」が分かる総合メディア
あしたの人事オンライン 「あした」を変える「人事」が分かる総合メディア









